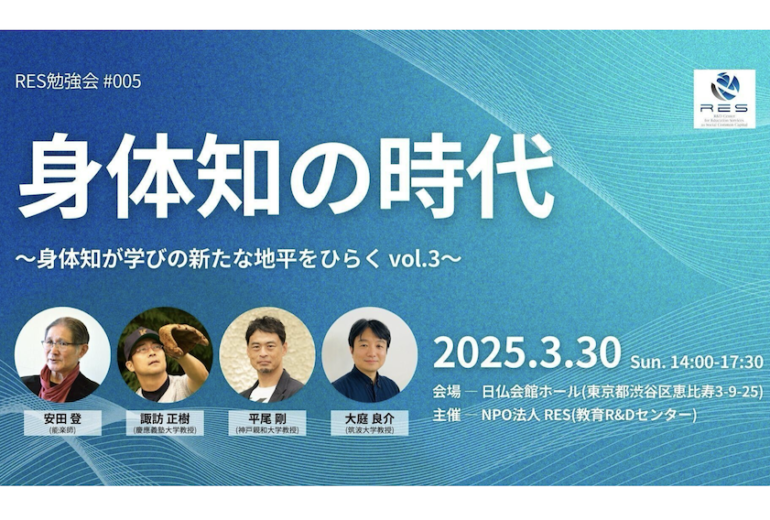キエラン・イーガン『想像力を触発する教育』にある少なくとも三つの主要な理念があることをご存知でしょうか?
- 教育の目的は、子どもを大人社会の規範、価値観、習慣に少しずつ適応させることだとするもの。(社会的要請)
- また、教育は子どもの精神にとって最良のものを与えるべきだとするもの。(文化的要請)
- さらに、精神は肉体と同じように成熟するまで段階的な過程を経るため、教育はこの段階的な発達過程をできるだけ助けるものだとするもの。(個別的要請)
(キエラン・イーガン『想像力を触発する教育』より)
社会的要請に基づく教育では、大人社会で重要とされる活動が何かによって、子どもが身につけるべき技能や知識、信条が決まってきます。たとえば、狩りが重要なら狩猟技術が、コンピューターが重要ならプログラミング技術が学習事項になります。
文化的要請に基づく教育では、子どもの精神を十分に開花させるような教育が求められます。理想の精神に必要なことが科学なのか、芸術なのか、道徳なのかによって学習事項が決まります。
個別的要請に基づく教育では、それぞれの成長段階で子どもの学習を助けるようなカリキュラムが提供されるべきとされています。生徒の精神はそれぞれ異なるため、生徒の違いに応じた教育が必要です。
現在の日本(あるいは世界)の状況を踏まえると、これらのうちどの要請に重点を置くべきかを決めることは、極めて困難です。大人社会で重要とされる活動は、将来の見通しが不確実である以上、確信をもって言えません。30年後にプログラミングが重要であると誰が断言できるでしょうか。また、子どもの精神を開花させる教育によって、子どもが本当に現在の資本主義が浸透している社会で生き残ることができるのか、これもまた不確かです。成長段階での発達過程をできるだけ助けるというのは良いとしても、一人ひとりの「自然な」「自発的な」発達に合わせた教育を公教育の体制で本当に提供できるのでしょうか。それぞれの理念には納得感があっても、実際には様々な論点に直面します。
この困難を乗り越えるには、教育という視点よりも学習という視点からアプローチした方が効果的ではないかと考えます。
教育と学習は切っても切り離せない関係にありますが、基本的な要請はそれぞれ別のところから生じます。基本的には、教育(つまりTeaching)は、生物としての人間が集団として生存確率を上げるために必要なことであり、学習(つまりLearning)は、個々の人間がそれぞれの生存確率を上げるために必要なことと言えます。集団としての方向が見いだしにくい環境にある以上、個々の人間が「生きるための力」とはどのようなものかを考えるところを起点に、時代にあった「教育サービス」のあり方を考えるべきです。